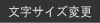|
戦後50年 あの日あの時 |
戦後五十年
延岡市 男性
宮崎空港の滑走路。その滑走路の下に、今でも我々の埋めた石ころがあるのだろうかと、ふと思うことがある。昭和19年から20年にかけて、第一宮崎国民学校の6年生だった。勤労奉仕なるもので、赤江飛行場に駆りたてられたのは、軍用飛行場の増設、延長の工事でもあったのだろうか。
我々には、そんなことは分からないが、とにかく軍用トラックに積み込まれた6年生、約180名が赤江の飛行場へ向かう。飛行場では作業の責任者の説明を受けて作業にかかる。赤子の頭ほどの石を埋め込む。その道具は直径1メートル位の、コンクリート円筒形のローラーである。真ん中に穴があり、それに鉄棒が通してあって、その両端に長い綱がかけてあり、これを両方に分かれて引っ張るのである。ローラーは静かに回りはじめ、並べられた石は次々に地下に埋まっていく。この石が、どのような効果があるのかわかるはずはない。炎天下、汗にまみれて、ただ黙々と綱を引っ張るだけである。
やがて石が埋められたあとは、作業員たちがコンクリートを流し込んで平らに、ならしていく。この過程からわれわれは、飛行機のえんたい壕掘りの場所に移動する。滑走路には、呑龍、銀河、靖国という爆撃機や何機かの戦闘機を見た。今、おもえば、これらの飛行機は、鹿児島の知覧や沖縄方面に飛んだろうと思う。
移動する際に何人かの飛行兵に会った。若くりりしい、あこがれの飛行機乗りの兵隊さん、羨望の目で見たものだった。
その時の年令推定が17、8才だろうか。「今からどこに行くと」と問うても黙として語らず、静かに笑みを浮かべながら、ポケットから携帯口糧の乾パンを出してくれた。一口大の固いものだったが、当時は食糧も逼迫しており、珍しくありがたく、とてもうまかった。
飛行帽の下に、日の丸の鉢巻きが見えた。特攻隊員であったろう、そう思った。彼も戦闘機もろとも、若い生命を捧げた一人であったかも知れない。
「コノシロ」少尉といった。その姓は忘れない。乾パンの味と、童顔だった隊員のことを思うと、あれから、どうなったのか、胸が痛む。
やがて、戦況もきびしくなりB29や艦載機のグラマン、カーチスなどの爆撃を受けるようになる。特に赤江の飛行場は艦載の波状攻撃が連日であった。黒煙が空を覆い、昼夜を問わず、集中的な攻撃にあった。そしてかなりの打撃を受けたのだろう。
赤江の飛行場には、二度と行くことはなかった。その後、どうなったのだろうと気にする前に、我々の身辺にも危険が迫ってきた。住んでいた瀬頭町は、赤江の対岸でもある。戦闘機、グラマン、カーチスは頭上すれすれに宮崎駅方面に舞い上がり、旋回しては一ツ葉に出て、ふたたび赤江に爆弾投下、そして機銃掃射を繰り返す。日本の飛行機は、何をしているんだと歯をかんだ。6年生の卒業式も、どうであったかよく覚えていない。
昭和20年5月、宮崎を逃れて以来、その後のことは全くわからない県北の北川に忍んだ。
電灯もない、もちろんラジオもない、途絶された山峡にきて、ホッとした3ヶ月後に終戦となる。そこは「野上」というところだった。戦火を逃れて来る場所には最適だと思った。不自由は覚悟の上で来た「野上」だが、宮崎市とは雲泥の差。でも、B29や艦載機のうるさい爆音にさいなまれることのない場所であることには間違いない。
戸数4戸、川辺にひっそりとたたずむ風情は12歳の俺には、チョッと淋しかった。
当時、父が転入届が受け付けられない。学校にも転入できないと言う。父母、弟と4人は幽霊人口として働かざるを得ないことになる。母と俺は、貯木場の現場で働く、弟は肋膜で、父が伴って病院通い。
「一体どうなるのか」戸惑いがあり、そして学校は行けるのか、小学6年を卒業して、高等科1年に2ヶ月足らずのまま、ツルハシ振って、貯木場での作業が毎日続く。馴れない仕事はすごくつらい、日給30円という仕事についた訳だ。
「勘定」というものを知った。野上から約1.7キロ、朝の食事は麦ばかりに塩、「食いたい、食いたい」ばかりの今の中学1年生、夜はタイマツの灯、やりきれないと思うと同時に「学校は」と想い、アメリカの進駐軍が視察に来た時、この1年がんばればどうにかなると思い、がんばった。白石の貯木場は、ダイナマイトの音で埋まったようなものだった。
そして、昭和21年4月に転校が許可され、俺は高等科1年、弟は小学4年生に編入することになった。1年遅れだが仕方のないことである。とにもかくにも、転入できただけでも、まずうれしかった。
登校した時、校門左側にあった「二宮金次郎」像の傍らに居た男子が声をかけてくれた。拠り所のない自分には、おどろきと、とてもありがたかった。
その男子が、学年を共にした「四郎」君であったのは今でも鮮明に焼きついている。あまり口数は利かないが、親身な「ポッポッ」と折れそうな自分に「生きる」という決心を与えてもらった。終戦直後、何もかも混乱して手探りの情況、「生きる」「学ぶ」環境は口には言えない程痛烈なものがあった。
誰も知らない地に来て生きる大変さ、言語に言い尽くせないものがある。「四郎」と会った、お互いに還暦の同窓会、俺達の青春は何だったのか、などと60年を振り返り、笑いで吹き飛ばす今の世情が、子や孫たちに、ほんとうに「生きていてよかった」という実感を味わってもらいたいナー。生涯学習フェスティバル産業祭の折に「四郎」と語った。
北川で結婚し、男、女、子どもは北川で育ち、俺の出た学校を卒業した。俺の「ふるさと」は無い。長崎の原爆で。
でも、二人の子どもは「ふるさと北川」をもっている。それだけが子どもに贈る「オレのふるさと、北川」である。
|
戦後50年 あの日あの時 |